「敷居が高い」という表現、よく耳にしますよね。
例えば「この店は敷居が高くて……」と言う時、その店が高級すぎて入るのが難しいという意味で使われることが多いです。
しかし、この使い方は以前、誤った使い方とされていました。
ところが最近、広辞苑第七版において、この意味が新たに追加されたのです。言葉の意味や用法は時代とともに進化するものですね。
今回は、「敷居が高い」の正しい意味や使い方、語源や言い換えについて詳しくご紹介します。
「敷居が高い」の意味とは
「敷居が高い」という表現は、元々「自分が不義理をしていてその家に訪ねづらい」「その場所が高級で敷居が高いと感じて入りづらい」という意味があります。
これまで、一般的には「高級すぎて入れない」といった意味合いが誤った使い方だとされていました。
元々の意味は「不義理をしてその家に行きにくい」というものであり、「自分には高すぎる」「レベルが高すぎる」という使い方は誤りだと考えられていたのです。
しかし、最近の調査結果では、実際には後者の使い方をする人の方が多いという結果が出ました。さらに、以前から「不義理」を理由にした使い方の根拠自体が不明確であることが指摘されています。
そのため、「敷居が高い」の「高級すぎて入れない」という意味が誤用とは限らないと考える人も存在していました。
2018年1月に発行された『広辞苑第七版』では、「高級すぎて、その家や店に入りにくい」という意味も正式に認められ、新たに加えられました。
「敷居が高い」の使い方
「敷居が高い」は、前述のように、「不義理をしていて訪れるのが気まずい」「あまりにも高級で行きづらい」という状況で使われます。以下の例文を通じて使い方を確認してみましょう。
例文:
- 借金を返していないので、彼の家に行くのは敷居が高い。
- 何年も先生と連絡を取っていないので、今更訪れるのが敷居が高いなぁ。
- あのレストランはとても高級で、敷居が高い。
- 高級な料亭は敷居が高い。
最初の2つの例では「不義理をしていて行きづらい」という意味で使われ、後の2つの例では「高級すぎて入りづらい」という意味で使われています。
「敷居が高い」の語源
「敷居が高い」という表現がなぜ「行きづらい」という意味を持つのかを理解するためには、まず「敷居」の意味を知る必要があります。
元々「敷居」とは、家の出入口に設置される横木のことです。今ではドアが一般的ですが、昔の日本家屋では引き戸や襖(ふすま)、障子を開け閉めする際に、下部に溝があり、その溝に収められる横木が敷居でした。
敷居は内と外を隔てる大切な役割を果たしており、家に入るためにはその敷居を越えなければなりません。
このような背景から、不義理をしていたり、あまりにも格式が高かったりすると、その家や店に足を踏み入れるのが気まずく感じるため、「敷居が高い」という表現が使われるようになったのです。
「敷居が高い」の別の言い方
「敷居が高い」という表現の意味や使い方は理解できましたか?
この表現が指す「高級すぎて行きづらい」という意味は、実は広辞苑の最新の版に追加されたばかりです。
そのため、使う際には「誤用だ」と思われることがあるかもしれません。しかし、今後はこの新しい用法が広がっていくことが予想されます。
とはいえ、まだ「敷居が高い」という表現を使うことに対して抵抗を感じる場合や、別の言い回しを使いたいときもあるでしょう。そんな時に役立つのが、以下のような言い換え表現です。それぞれの表現が持つニュアンスを理解し、シチュエーションに合わせて使い分けることが大切です。
- 格式が高い
「格式が高い」という表現は、主にその場所や人が持つ高い品格や地位を指す言葉です。「敷居が高い」と似た意味で使われ、何かが自分の手に届かないほど高いレベルにある、という意味合いを持っています。例えば、高級レストランや格式のある家などに対して「格式が高い」と言うことで、相手に敬意を表しつつ、行きづらさを表現することができます。 - レベルが高い
「レベルが高い」は、物事の難易度や質が非常に高いことを表現する言葉です。これを「敷居が高い」の意味の代わりに使うときは、その場所や機会が自分には合わない、または自分には手が届きにくいという感覚を伝えることができます。特に、競争が激しい分野や、専門的な知識やスキルが求められるシチュエーションに適しています。 - 手が届かない
「手が届かない」は、文字通り「自分の力では達成できない」「近づけない」という意味で使います。例えば、高級なブランド品や憧れの人、特別な地位にあるものに対して、「手が届かない」と言うことで、その目標や場所に行きづらい、という気持ちを表すことができます。物理的に手が届かないと感じることを強調することで、さらに難しさや距離感を伝えることができます。 - 高嶺の花
「高嶺の花」という表現は、通常「手が届かない美しいもの」や「自分には相応しくないもの」に使われます。この言葉には、好意を抱く相手が非常に高貴で手に入らない存在であるという意味が込められています。物理的な距離だけでなく、社会的・心理的な距離も含めて「敷居が高い」という感覚を表現するのにぴったりです。 - 雲の上の存在
「雲の上の存在」は、文字通り「自分の存在とはかけ離れているほど高い地位にある存在」という意味で使います。この表現は、あまりにも遠い存在、近づけないと感じる相手に対して使います。特に、憧れの人や尊敬する人物、非常に成功している人に対して使うことが多いです。自分には手が届かない存在という感覚を、より強調する際に使います。 - 分不相応
「分不相応」は、自分の身の程を超えている、または自分に相応しくないという意味です。これを使うことで、何かが自分には過ぎたものである、または自分にはふさわしくないという感覚を表現できます。「敷居が高い」が持つ「自分には高すぎる」という意味を伝える際にぴったりな言い回しです。
これらの言い換え表現は、状況や対象によって使い分けることで、より適切なニュアンスを伝えることができます。
たとえば、高級レストランに対して「敷居が高い」と感じる場合は「格式が高い」「レベルが高い」が適しているでしょう。
一方で、憧れの人に対して感じる距離感を表現したいときには「高嶺の花」や「雲の上の存在」が適しています。
言い換え表現をうまく使いこなすことで、さらに豊かな表現ができるようになるでしょう。
まとめ
「敷居が高い」という表現は、従来の「不義理をして訪れづらい」という意味に加え、最近では「高級すぎて入りづらい」という意味も正式に認められました。
広辞苑の最新版で新たに追加されたこの意味が、今後ますます普及していくことが予想されます。
まだ誤用だと思われがちな場合もありますが、両方の意味を理解して使いこなすことが大切です。
日常生活での使い方をしっかりと覚えて、適切に使えるようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
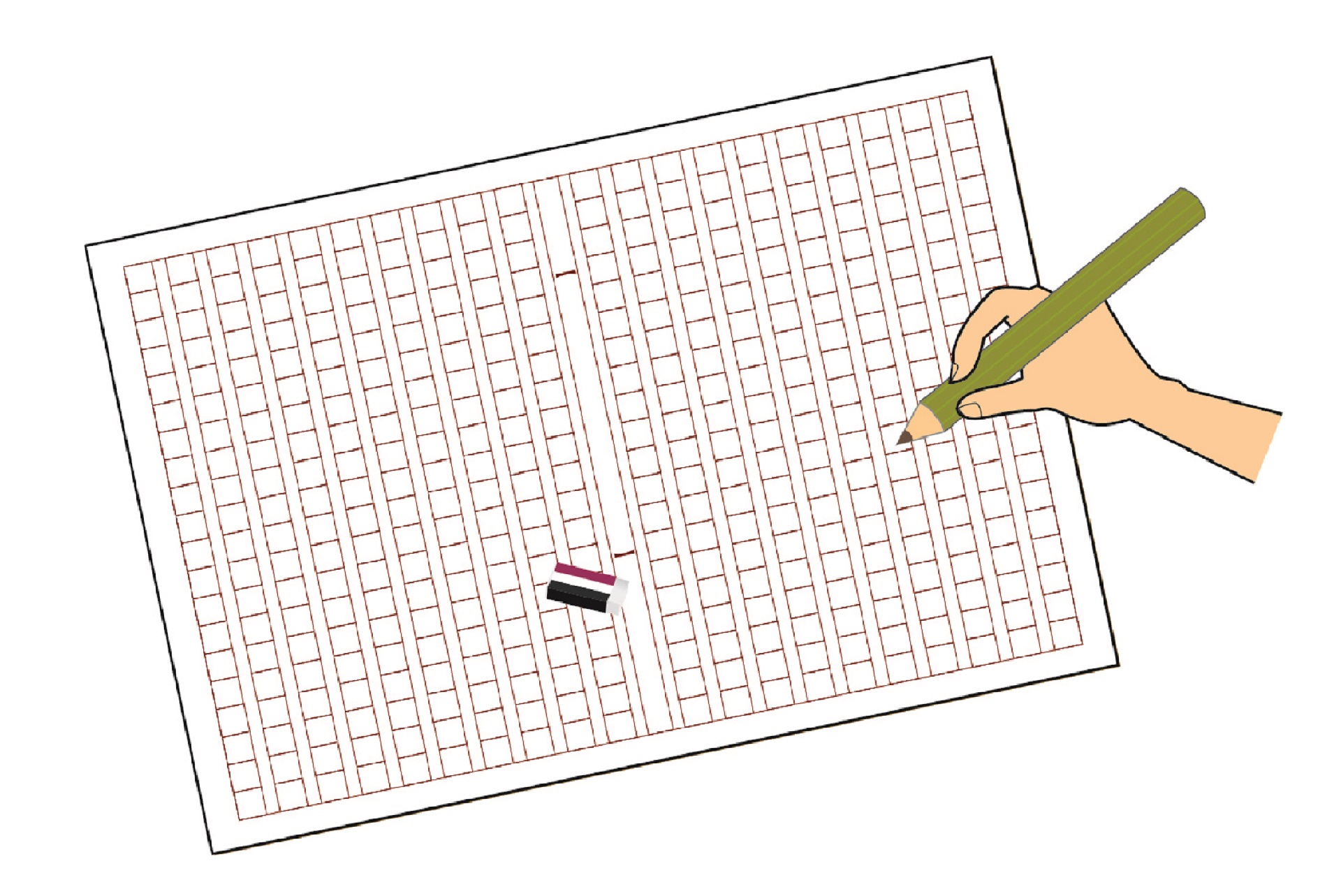

コメント