「悪しからず」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
たとえば、「~ですので、悪しからず。」といった形や、店頭で「こちらの商品は売り切れです。悪しからずご了承ください。」と案内されているのを見たことがあるかもしれません。
この表現、どことなく昔の人が使いそうで、少し古風な印象を受けますね。
聞いたことはあっても、自分では使ったことがないという方も多いのではないでしょうか。
ところで、「悪しからず」の正しい意味をご存じですか?
なんとなく使い方を知っているようで、実際には詳しく理解していない方も少なくないようです。
そこで今回は、「悪しからず」の本来の意味や使い方、さらに目上の人に対して使用できるかどうかを詳しく解説してきます。
「悪しからず」の意味
まずは「悪しからず」を辞書で調べてみましょう。
「悪しからず(あしからず)」は、相手の期待に応えられない場合などに使う表現で、「気を悪くしないで」「悪く思わないで」といった意味があることがわかります。
つまり、この言葉は「悪く思わないで」「気を悪くしないで」といった意味を持っているのです。
そのまま覚えておくと便利ですが、少しだけ詳しく説明しますね。
「悪しからず」という表現は、古語の形容詞「悪し(あし)」の未然形「悪しから」に、否定の助動詞「ず」が加わったものです。
ここで少し古文の話が出てきましたが、難しいことはありません。
「悪し(あし)」という言葉は、ここでは「悪く思う」「不快に感じる」といった意味で使われています。
それを否定することで「悪く思わない」「気を悪くしない」といった意味になります。
さらに、この表現の後に続く部分は省略されることが多く、その場合には「悪く思わないでください」「気を悪くしないでください」といった丁寧な意味合いになるのです。
「悪しからず」の使い方
「悪しからず」は「気を悪くしないで」「悪く思わないで」という意味を持っています。
もう少し詳しく言うと、「悪意はありません。やむを得ないことなので、どうかご理解いただければ」という気持ちを表しています。
この表現は、相手に対して不快な思いをさせてしまうことがわかっているけれど、どうしても避けられない状況にあるときに使うべきです。
急な予定変更や、やむを得ず中止することを伝える際などに、相手への謝罪の気持ちを込めて使えます。
ただし、明らかに自分に非がある場合や、しっかりと謝罪すべき場面では「悪しからず」を使わないようにしましょう。
【例文】
- 「先程はお電話に出られなくて申し訳ありませんでした。運転中でしたので、悪しからず。」
- 「出張のため出席できませんが、どうぞ悪しからず。」
目上の人に使える?
「悪しからず」は目上の方に対して使っても良い表現なのでしょうか?
たとえば、仕事の場面で上司やお客様、外部の人には敬語を使うことが求められますよね。
その中で「悪しからず。」だけで終わると、少し唐突な印象を与えるかもしれません。
この言い回しが丁寧でないのでは?と感じることもあるでしょう。
結論を言うと、「悪しからず」を目上の人に使うこと自体は失礼ではありません。ただし、使い方には注意が必要です。
「悪しからず」は、もともと「気を悪くしないでください」という意味で、謝罪や配慮を表す丁寧な言葉です。
しかし、文が突然終わるように感じられ、「~、悪しからず。」と言うと相手が失礼だと受け取ることもあります。
そのため、より丁寧に「悪しからずご了承ください」などと表現する方が適切です。
【例文】
- 悪しからずご了承ください。
- 悪しからずご承知おきください。
- 悪しからず、ご容赦願います。
まとめ
今回は「悪しからず」の意味や使い方について解説しました。この表現は、相手に不快な思いをさせることがある場合に使うもので、やむを得ない事情があることを伝えるための丁寧な言葉です。ですが、適切な場面や使い方を理解していないと、相手に不快感を与えることもあるため注意が必要です。
また、目上の人に使う際には、相手が失礼だと感じないよう、少し工夫して表現を丁寧にすることをお勧めします。例えば、「悪しからずご了承ください」など、より柔らかい表現にすることで、失礼にならず、きちんとした印象を与えることができます。
「悪しからず」は、使い方次第で非常に丁寧で配慮のある言葉になりますので、シチュエーションをしっかりと見極めて、上手に使っていきましょう。
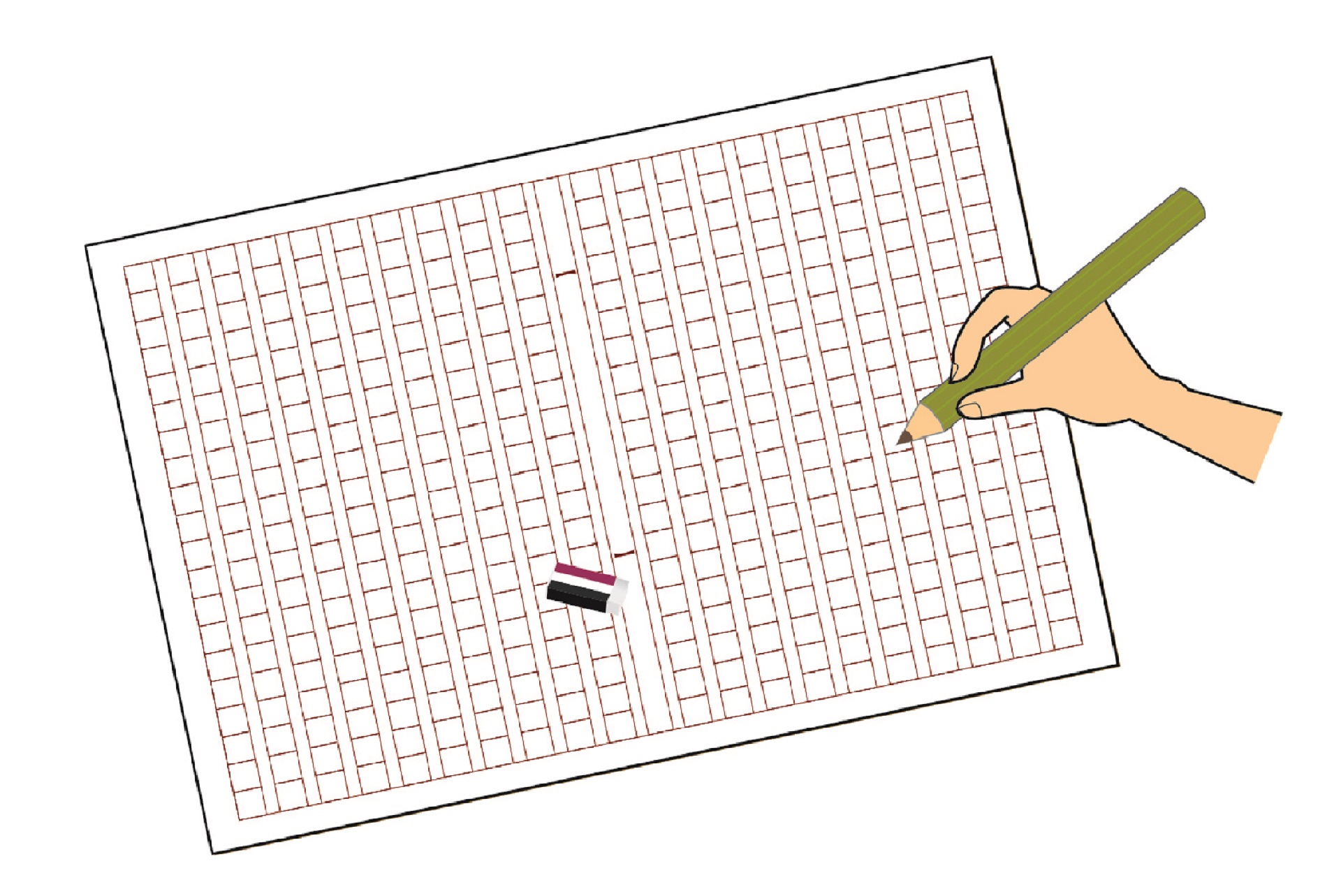

コメント